理解を求められる、社交ダンスの音楽
世の中には、すでに様々な音楽の入門書があると思います。そして社交ダンスの音楽についても、入門書があったりします。社交ダンスでは、音楽に合わせて踊ることが重要であり、ある程度ダンス音楽に対して理解することが求められるようです。
ここでは簡単に社交ダンスの音楽について、ご紹介したいと思います。
よくあるダンス曲のメロディー構成は、次のようなものになります。
- イントロ(4小節以上)。
- 「1コーラス目」:A-A'-B-A"(32小節)。
- 間奏(0から4小節以上)。
- 「2コーラス目」:A-A'-B-A"(32小節)。
- エンディング(4小節以上)。
上記の「A-A'-B-A"」は、起承転結と考えると良いでしょう。この「まとまり」をコーラスと呼びます。一般的にダンス曲においては、コーラスを2回繰り返して1曲となります。つまり、2番と4番の2コーラスとなります。
ダンス曲は「だいたいこんな感じ」でメロディーが演奏されると知っているほうが、曲に合わせてダンスを踊れるでしょう。
3拍子のワルツ
音楽理論では、拍子という言葉が出てきます。この拍子という言葉は、音楽理論以外のところでも、例えば身近なところでも使われています。例えば3・3・7拍子です。みんなで「お手」を拝借して手拍子する際、3・3・7拍子がよく使われています。
そして社交ダンスのワルツでも、拍子という言葉が出てきます。
実はワルツという種目は、
社交ダンスの中で、唯一「3拍子の曲」に合わせて踊る種目です。
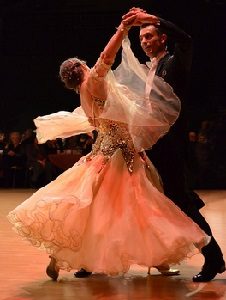
つまりワルツを上手に踊りたいなら、3拍子を理解しておくことが大事です。
ボールルーム・ダンステクニックのワルツの部には、
「1・2・3」と書かれてあります。
これらの数字の上にはステップ(歩順)と書かれてあります。それぞれの数字に対応して、一歩一歩の説明がされている訳です。
ワルツを踊る際、3拍子を実感しつつ踊ってみましょう。


