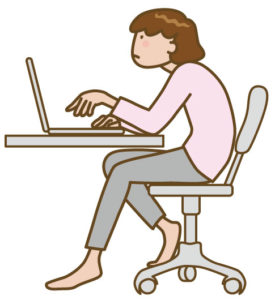衝撃など、ハードディスクがクラッシュした原因
最大のトラブル・ハードディスクのクラッシュ

ハードディスクの中身は、
- 回転する記録用の磁気円盤
- 振り子のように左右に移動できる読み書きヘッド
- それらを動かすモーターと制御基盤
以上の物より、成り立っています。
通常は、「データを読み書きする役目を持つヘッド」が「データを記録する磁気円盤」から浮いた状態で、「データの読み書き」を行ないます。
しかし何らかの原因で、
そうすると、修復不能な故障となってしまいます。
この故障を、クラッシュと言います。ハードディスクにおける最大のトラブルと言えます。
もしもハードディスクから「カタカタ」と音が聞こえた時は、既にハードディスクがクラッシュしている可能性があります。その時は、専門の業者に調査してもらうほうが良いでしょう。
クラッシュの原因
ハードディスクのクラッシュは「強い衝撃」や「ホコリ」「湿度の異常」などが原因として考えられます。その他、長い間電源を入れていないハードディスクでも発生する、と言われています。
衝撃
ハードディスクが壊れる原因として、衝撃が一番の原因だそうです。
パソコンを起動している時は、ハードディスクは高速に回転しています。この時、ちょっとした衝撃で読み書き用ヘッドとディスクが接触すると、ディスク表面を削ってしまいます。そうすると、ハードディスクが壊れてしまいます。
もちろん、パソコン内部でも衝撃対策が行なわれています。よって普通に使っていれば、簡単に壊れることはないでしょう。
ハードディスクは、非常に精密な機械です。ハードディスクにおいては振動対策を施していますが、それでも確実な対策かと言うと、そうではないようです。
なお、パソコン本体も精密な機械です。よって、出来る限り振動や衝撃を避けるべき機械と言えます。
ホコリ
読み書き用ヘッドと磁気円盤の間隔は、タバコの煙の粒子くらいと言われるほどに、狭い隙間です。なので目に見えないくらいのホコリでも、その間に詰まってしまうと、クラッシュの原因となります。
ホコリからハードディスク装置を守るため、ハードディスクの全体は、金属製のケースの中に密封されています。
ちなみに工具さえあれば、簡単に金属製のケースを開封できます。そして分解もできます。
ただし一度でも分解してしまうと、ホコリなどが付着してしまい、組み立てたとしも正常に使用できなくなってしまいます。
結露
特に冬の寒い時期に、問題となるのが結露です。
例えば、屋外の非常に寒い場所から暖かい室内にハードディスクを移動させると、温度が上昇するに伴って、ハードディスク内部に結露が生じる可能性があります。
このまま起動したりすると、ハードディスクは壊れてしまいます。
数時間は室内にそっと保管しておき、室温に慣らしてから動作させるほうが良いです。
しばらくぶりに動作させる事
稀な事例として、ハードディスクを「しばらくぶり」に使うと、ハードディスクが傷つくことがあるそうです。
ハードディスクのヘッドでは、滑らかにするために潤滑油を使っています。この潤滑油が使われない状態が続くと、ヘッドに溜まってゆき、動かなくなったりします。そんな時に、たまたま動かしたらハードディスクを傷つける、ということです。
「しばらくぶり」の使用とは、例えばずっとハードディスクを使わずに、1年に1回、1文字だけ書き込んだら、こういう状態になるそうです。
※最新のハードディスク機器では、改善されているかもしれません。耐久性に関して、商品情報をご確認ください。