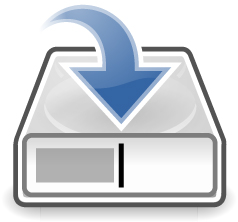知っておきたい、ハードディスクの仕様
ハードディスクの形状

ハードディスクの形状には、内蔵型ハードディスクと外付け型ハードディスクがあります。
それぞれのハードディスクには、どのような特徴があるでしょうか?
内蔵型
内蔵型ハードディスクは、パソコン本体の内部に取り付けて使用するハードディスクです。
デスクトップパソコンやサーバ用パソコンでは、磁気ディスクの直径が3.5インチのハードディスクが主流です。IDE規格とSCSI規格の2種類があります。
ノートパソコンでは、磁気ディスクの直径が2.5インチのハードディスクが主流です。IDE規格が採用されています。
内蔵型ハードディスクのメリットとしては、まず値段が安い点を挙げられます。
そして、パソコン周辺にハードディスクを設置するスペースも不要です。ただしハードディスクを設置するには、パソコン内部に空きスロットが必要です。
なお、ハードディスク機器を交換する際は、パソコン本体のケースを開ける必要があります。
外付け
外付けハードディスクは、パソコンの外部に設置して使用するハードディスクです。
外付け型には「USB規格」「IEEE1394規格」「SCSI規格」などがあります。パソコンとハードディスクを専用ケーブルで接続します。
ただしパソコン側に接続ポートがない場合では、それぞれの拡張カードを装着する必要があります。
外付けタイプの特徴は、パソコンとハードディスクをケーブルで接続するだけという点です。接続するだけなので、接続や増設を簡単に行なえます。
ただし、内蔵型ハードディスクよりも値段が高額なことが多いです。そしてパソコン周辺に、ハードディスクを設置するスペースが必要になります。
ハードディスクのディスク枚数と容量
ハードディスクの中には、磁気ディスクが組み込まれています。ハードディスクの容量は、これらの磁気ディスクに「どれくらいの情報を書き込めるか」ということで決まります。
ハードディスク容量を大きくしようとした場合、磁気ディスクの記録密度を高くする方法と、磁気ディスクの枚数を増やす方法があります。
全く同じ記録密度の場合、ディスク枚数が2倍になれば、ハードディスク容量も2倍になります。
ディスク枚数を増やしてハードディスク容量を大きくすることは手軽です。ただし、電気の消費量が大きくなり、発熱しやすくなります。
また、ディスクの数が多いので、パソコンから発する音が大きいなどのデメリットもあります。
ケースの中に納まる枚数にも、限度があります。なのでディスク枚数は、通常では1枚から4枚です。
実際の製品では、ハードディスク内のディスク枚数がハードディスク装置自体の価格に反映されています。
同じハードディスク容量の装置なら、ディスク枚数が多いタイプのほうが、少ないタイプよりも低価格です。
つまり、記録密度の大きいディスクを使用してハードディスク容量を大きくした製品は割高になる、ということです。
同じ容量のハードディスク装置でも、小さいほど値段が高いという理由も同じとなります。
ハードディスクの回転数
ハードディスクに入っている情報を読み出したり書き込んだりするためには、磁気ディスク上の目的の位置に、読み書き用の磁気ヘッドを移動させる必要があります。
磁気ヘッドと磁気ディスクとの情報の「やり取り時間」は電気的な処理のため、ごく一瞬で済みます。そのため、「ハードディスクを読み書きする速さ」は、磁気ヘッドが磁気ディスクの目的の位置に「いかに早くたどり着くか」ということで、決まります。
そこで重要となる点が、磁気ディスクの回転数です。
磁気ヘッドの移動は、磁気ディスクの回転数と組み合わされています。そのため、磁気ディスクの回転数が多いほど、「目的の位置」にたどり着くのが早くなります。
なお、磁気ディスクの回転数は、通常4500(回転/分)から10000(回転/分)です。この回転数が多ければ多いほど、「読み書きする速さ」に優れています。
ただし、ハードディスク装置自体の値段は高くなります。
回転を速くした場合のデメリット
「読み書きする速さ」を優先すると、回転をどんどん速くすれば「それで良い」と思うでしょう。
ですが回転を速くすれば、それにともないデメリットも発生します。
一つは、バッテリーの問題です。
ハードディスクの磁気ディスクは、通常ずっと回転し続けています。そのため例えばノートパソコンでは、そのモーターで消費される電力は、液晶ディスプレイと同じくらいに消費されると言われています。
ハードディスクが消費する電力量は、ノートパソコン全体の10%から15%を占めている、という意見があったりします。
もう一つのデメリットとして、高速で磁気ディスクを回転させた場合には、ディスクのクラッシュ問題が出てくるようです。
※この記事は2007年当時の記事になります。