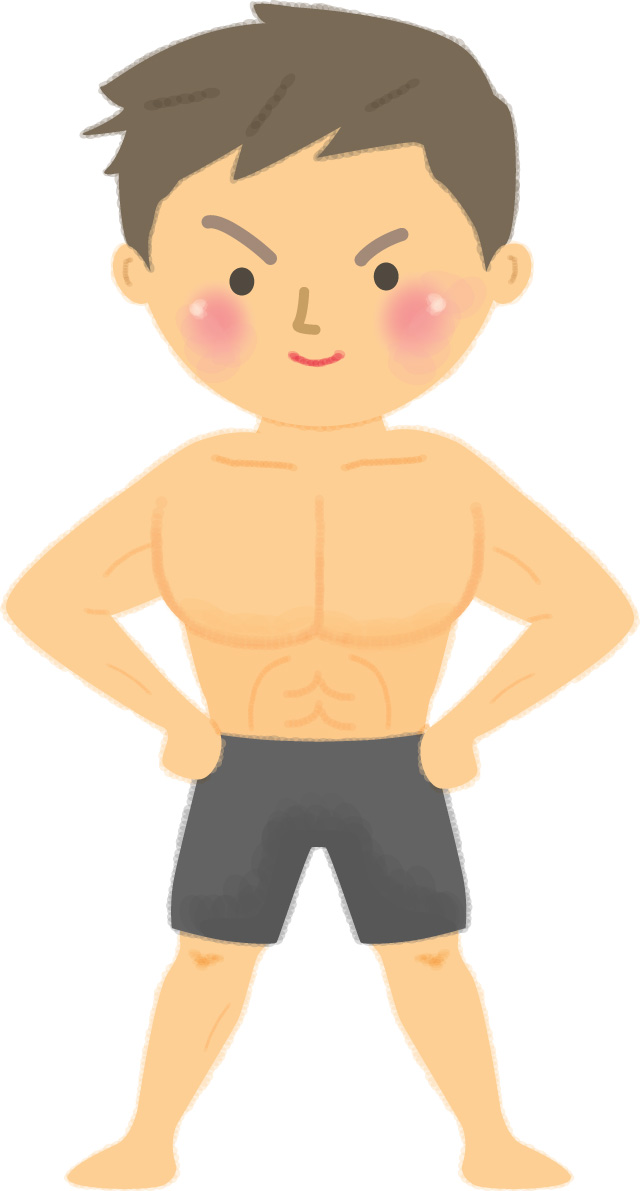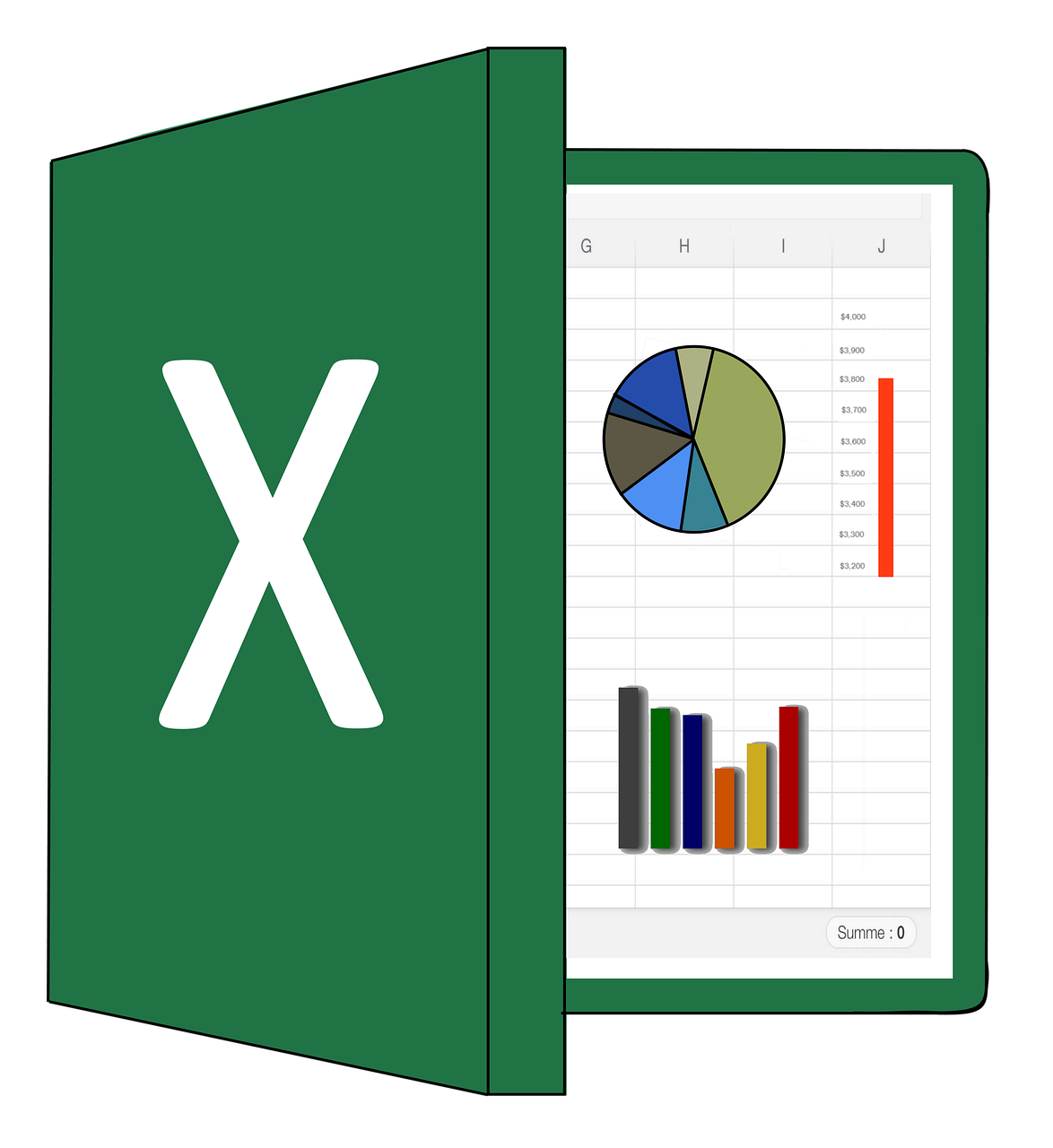誕生のきっかけなど、バービー人形の歴史
バービー人形が誕生したきっかけは、何でしょう?
娘バーバラのために購入した、ドイツの人形リリがきっかけでした。
人形リリはアメリカ人向けにデザインを変えて、バービー人形となりました。
バービー人形が誕生したきっかけ

バービー人形は、ドイツの人形ビルドリリ(Bild Lilli)をモチーフにして生まれました。
この人形リリは、マテル社の創業者ルース・ハンドラー(Ruth Handler)氏が、ヨーロッパを旅行中に、娘バーバラのために購入した物でした。
プロポーション抜群なリリ人形は、大人の男性をターゲットに作られました。
しかし、ファッションセンスが良いリリ人形は、女の子の間でも人気となりました。
マテル社は、アメリカでのリリ人形の販売権を獲得しました。
アメリカ人向けにデザインを変えて、娘のバーバラという名前にちなみ、バービー(Barbie)と名付けられました。
バービーは、1959年3月9日に「ニューヨークのトイフェアー」にて、デビューとなりました。
本名は、バーバラ・ミリセント・ロバーツ(Barbara Millicent Roberts)です。
ファッションモデルをしている17歳という設定になります。
娘への愛と、女性の可能性を広げるというビジョン
バービー人形が誕生した「精神的なきっかけ」は、以下の二つにあったと言えます。
- ルース・ハンドラー氏の娘への愛。
- 女性の可能性を広げるというビジョン(未来像)。
バービー人形は、1959年にアメリカのルース・ハンドラー氏によって発明された、世界的なファッションドールです。
しかし、その発明の背景には、ルースが自分の娘バーバラとその友人たちの遊びを観察したことが、大きく関係しています。
ルースは、自分の娘が、大人になりきって遊ぶための赤ちゃんの人形に限られていることに、気づきました。
そんな状況において、ルースは、娘たちが自分たちの将来の夢や願望を表現するために、紙で作った服を人形に着せ替えて遊んでいるのを見ました。
ルースは、女の子たちが自分のアイデンティティーやキャリアを探求することを助けるような、大人の女性の姿をした人形が必要だと感じました。
そこで、彼女はドイツで見つけたビルドリリ(Bild Lilli)という人形を参考にして、バービー人形を開発しました。
バービー人形は、様々な職業や趣味に挑戦することができる、自立した女性の象徴として、世界中の女の子たちに受け入れられました。
バービー人形は、医師や弁護士、宇宙飛行士などの職業にも挑戦しました。
これは、女性が男性と同じように社会で活躍できることを示すとともに、子どもたちに自分の夢や目標を持つことを励ましました。
女性の自己表現や自信を高めるため
また、バービー人形は、ファッションや美容に関する文化やトレンドを発信することで、以下の事に寄与したと言えます。
- 女性が自己表現すること。
- 女性が自信を高めること。
バービー人形は、時代や国に合わせて様々なスタイルやアクセサリーを身につけました。
これは、女性が自分の好みや個性を自由に表現できることを示すとともに、子どもたちに自分の美しさや魅力を認めることを教えました。
バービー人形の変化の歴史
バービー人形は、時代と共に多くの変化や進化を遂げてきました。
バービー人形は、その時代の流行や価値観を反映しながらも、常に自分らしく生きることをメッセージとして、伝えてきました。
そういう事より、バービー人形は単なるおもちゃではなく、女性の歴史や社会の変化を象徴する存在と言えます。
1960年代、黒人のバービー人形が登場
1960年代には、黒人のバービー人形が登場して、多様な人種や文化を表現しました。
例えば、1968年に発売された黒人のバービー人形「クリスティ」は、当時のアメリカで起こっていた公民権運動や黒人の自立を象徴するものでした。
このようなバービー人形は、異なる人種や文化に対する理解や尊重を促す役割を、果たしました。
1970年代、オリンピック選手のバービー人形が登場
1970年代には身体能力や健康に対する意識が高まったことに応えて、スポーツやダンスなどの活動的なバービー人形が発売されました。
この時期に登場したバービー人形の中には、オリンピック選手やバレリーナなどがあります。
これらのバービー人形は、女性の社会進出や自己表現の可能性を象徴するとともに、女性の美しさや健康への関心を反映しています。
1980年代、宇宙飛行士のバービー人形が登場
1980年代には、キャリアウーマンや政治家などの社会的なバービー人形が増えました。
これは、女性の社会進出や自立の象徴として、バービー人形が変化していったことを示しています。
例えば1985年には、宇宙飛行士のバービー人形が発売されました。
このようなバービー人形は、女性がどんな職業にも就けるというメッセージを伝えるとともに、子どもたちの夢や可能性を広げる役割を、果たしました。
1990年代、大統領候補のバービー人形が登場
1990年代には、環境問題や平和運動などの社会的なテーマに関わるバービー人形が作られました。
これは、当時の世界的なエコロジー運動や軍縮運動の影響を受けたもの、と考えられます。
例えば1990年には、「バービー・フォー・プレジデント」というバービーが発売されました。
※おそらく、「バービーが大統領になってほしい」という意味だと思います。
このバービーは、女性の政治参加を促進するとともに、環境保護や平和構築などのメッセージを伝えることを、目的としていました。
2000年代以降、バービーのオンラインゲームやアプリが登場
2000年代以降は、インターネットやデジタル技術の発展に伴って、オンラインゲームやアプリなどの新しいメディアで、バービー人形を楽しむことができるようになりました。
このことは、バービー人形の魅力や可能性を広げるとともに、消費者のニーズや嗜好に応えるための戦略と言えます。
例えば、オンラインゲーム「バービー・ドリームハウス・アドベンチャーズ」では、バービーの家や友達と一緒に、様々なアクティビティを楽しむことができます。
このゲームは、バービー人形を手に取って遊ぶことが難しい場合や、自分の好みに合わせてカスタマイズしたい場合に便利です。
また、アプリ「バービー・ファッションクローゼット」では、バービーの服や髪型を自由に変えることができます。
このアプリは、バービー人形のファッション性や多様性を高めるとともに、消費者の創造力や表現力を刺激します。
以上のように、新しいメディアでバービー人形を楽しむことは、バービー人形の魅力や可能性を広げるとともに、消費者のニーズや嗜好に応えるための戦略と言えます。
バービー人形の「人気の変遷」

バービー人形は、1959年にアメリカのマテル社が発売したファッションドールです。
バービー人形の「人気の変遷」を、独自の視点で考察してみましょう。
※バービー人形の「人気の移り変わり」については、あまり情報を見つけられませんでした。
ここでの考察は、参考程度にしてください。
1960年代、黄金期
1960年代は、バービー人形の黄金期と言えます。
アメリカの若者文化が世界に広がり、バービー人形はその象徴の一つとなりました。
バービー人形の、様々な職業や趣味に挑戦する姿が、女性の自立や多様性を表現していました。
そんなバービー人形は、世界中の女の子たちの憧れとなりました。
1970年代、危機
1970年代は、バービー人形の危機と言えます。
アメリカでは、フェミニズムや反戦運動が高まり、バービー人形は、その価値観に合わないと批判されました。
バービー人形は、白人中産階級のステレオタイプや消費主義を助長すると見なされました。
また、バービー人形は多くの競合商品に対しても、少しずつ劣勢となってゆきました。
1980年代、復活
1980年代は、バービー人形の復活と言えます。
マテル社は、バービー人形のイメージを刷新しました。
バービー人形は、より現代的でスポーティなファッションやアクセサリーを身につけました。
バービー人形は、より多様な肌色や髪型を持つようになりました。
そんなバービー人形は、新たな市場を開拓しました。
1990年代、再危機
1990年代は、バービー人形の再危機と言えます。
アメリカでは、政治的正しさや環境問題が注目されました。
そんな社会状況の中、バービー人形の理想化されたボディやライフスタイルが、女性の自己肯定感や社会的責任感に悪影響を与える、と非難されました。
長い脚、細いウエストという理想化されたボディは、一部の人々にとっては現実的ではないイメージです。
そのため、女性たちの自己肯定感に悪い影響を与える、と指摘されました。
豪華なファッションや成功したキャリアを持っているという理想化されたライフスタイルは、一部の人々にとっては現実離れしています。
そのため、社会的責任感に対する誤った期待を生む、と指摘されました。
また、バービー人形は、よりリアルなドールやキャラクターグッズにも負けました。
2000年代、変革
2000年代は、バービー人形の変革と言えます。
マテル社は、バービー人形のブランド力を高めるために努力しました。
バービー人形は、映画やテレビ番組に出演しました。
バービー人形は、有名なデザイナーやセレブリティとコラボレーションしました。
バービー人形は、インターネットやソーシャルメディアでコミュニケーションを取り始めました。
2010年代、再変革
2010年代は、バービー人形の再変革と言えます。
マテル社は、バービー人形の多様性と包容性を強調しました。
バービー人形は、より幅広い体型や身長、障害を持つようになりました。
バービー人形は、より多くの文化や宗教、国籍を表現するようになりました。
そんなバービー人形は、より多くの役割やメッセージを伝えるようになりました。
最初の日本では、人気がなかったバービー人形
ところで日本でも、マテル社から販売されているバービーは、女の子に大人気です。
しかし最初は、人気がなかったようです。
1960年代、あんまり人気がなかった「アメリカのバービー」
日本では、1960年頃から「アメリカのバービー」そのままの姿・形で、発売されました。
しかしあんまり人気が出ず、リカちゃん人形の登場により日本から消えていきました。
「アメリカのバービー」が日本で人気が出なかった理由としては、「日本の子ども」の美意識と合わなかったことが挙げられます。
バービーは、西洋的な容姿やスタイルを持つ人形でした。
なので、「日本の子ども」の多くは、それに親しみや憧れを感じなかったようです。
また、バービーは、大人びた雰囲気やファッションを持つ人形でした。
「日本の子ども」の多くは、それに違和感を感じたかもしれません。
リカちゃん人形については、1967年に日本で初めて登場しました。
リカちゃん人形が日本で人気が出た理由としては、「日本の子ども」の美意識や価値観に合致したことが挙げられます。
リカちゃんは、日本的な容姿やスタイルを持つ人形でした。
「日本の子ども」の多くは、それに親しみや共感を感じたようです。
また、リカちゃんは、子どもらしい雰囲気やファッションを持つ人形でした。
「日本の子ども」の多くは、それに可愛らしさや懐かしさを感じたのでしょう。
1980年代、再度日本へやってきたバービー人形
1980年代には、バービーは「日本人好み」に変身しました。
マテル社がタカラと提携することで、再度日本へやってきました。
しかしその後、バービーは、まるでジェニーと名前を変えて販売されたような状況に、なりました。
その当時、バービー人形の製造元であるマテル社と日本のタカラ社との契約が、1986年に終了しました。
そのため、タカラ社は独自にジェニー人形を開発しました。
ジェニー人形はバービー人形と似ていますが、顔や体型、服装などに日本の文化や嗜好を反映させています。
そんなジェニー人形は日本市場で大きな成功を収め、バービー人形よりも人気が高くなりました。
以上より、バービー人形はジェニーと名前を変えたのではなく、ジェニーという別の商品が登場した、と言えます。
1990年代、バービー人形の売り上げが減少
その後、マテル社はバンダイとも提携して(1999年当時)バービーを売り出しましたが、当時あんまり成功しなかったそうです。
バービー人形の売り上げのピークは、1990年代の半ばでした。
その後、バービー人形の売り上げは減少してゆきました。
近年、再び注目されているバービー人形
売り上げが減ったと言われているバービー人形ですが、例えば、2020年の売り上げは増えた、と言われています。
近年再び、バービー人形に注目が集まっています。
バービー人形は多様な肌色や体型、職業などを取り入れており、現代の女性のライフスタイルや価値観に合わせて進化しています。
これは、バービー人形のブランドイメージを高めるとともに、幅広い層の消費者に訴求する効果があると思います。
今後も、バービー人形は社会や文化の変化に対応しながら、ファンの期待に応える商品を提供していくでしょう。
実は、日本で作られていたバービー人形
最後に、バービー人形の生産に関する歴史を言うと、バービー人形は、実は「日本生まれ」でした。
逆輸入ということになります。
初期の(1960年代の)バービー人形は、玩具問屋の株式会社国際貿易が、日本で生産していました。
バービー人形の箱の文字や服に付いているタグなどは、英語で書かれていました。
なので、アメリカで製造されていると思いがちですが、実際は日本で作られていました。
バービー人形はアメリカ製(マテル社)だから、値段が高いのか?
当時、そう思っていた人もいたようです。ですが実際は、そうではありませんでした。
以上、バービーの着せ替え人形には、色々と歴史があったようです。